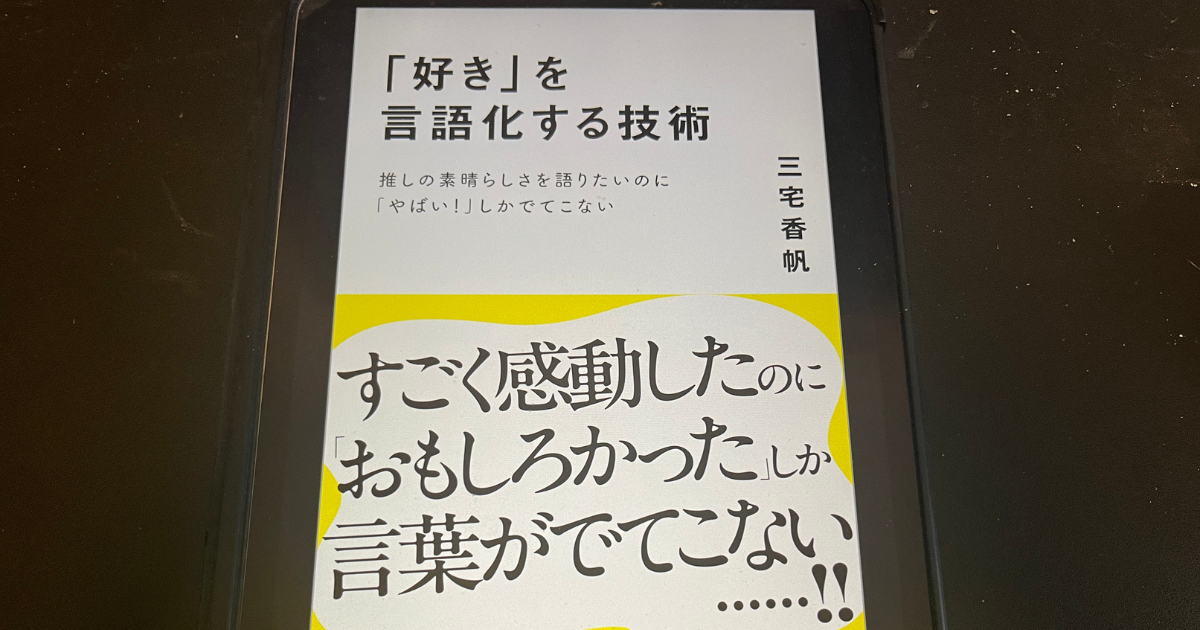
先日以下本を読了したのですが、ブログ発信する上で色々参考になったのであれこれ残そうとオモイマス。
リンク
なぜ「好き」を言語化するの?
- 冷静に自分の好みを言語化することで、自分の理解も深めることができる
- 自分が自分に対して信頼できる「好き」をつくることができる
- 好きは「儚く」「簡単に揺らぐ」から言語化する
- 他人が「駄作じゃん」と言ったのを聞いた途端、急に好きかどうかわからなくなることはあるある。
- 「好き」は揺らぐもの。「好き」は一時的な儚い感情。
- 儚いからこそ、鮮度の高いうちに、自分でなぞって理由を言語化して保存しておく。
- いつか好きじゃなくなっても「ああ、たしかにこの時期、私はこういうものが好きだったな」と思い出せるようにしておく。
「好き」を言語化するには?
- 「自分だけの感想」が大切
- 周囲が言っていることではなく、自分オリジナル感情を言葉に
- ありきたりワード「泣ける」「やばい」「考えさせられた」は避ける。
- 感想を「妄想力」でふくらませる
- 妄想だから正しくなくていい。客観的とかも気にしないで良い。
- なんでよかったのかな?という思考で妄想をふくらませる
- 良かった箇所の具体例を細かくあげる
- どこが最高なのか細分化する。オリジナリティは細かさに宿る
- メモで沢山書いて、孤独に一人でどこが気に入ったか考える。
- どうしてその感情を抱いたか?考える
- 面白さとは「共感」か「驚き」からくる。
- ネガティブ感情なら「不快」か「退屈」
- 「共感」なら自分の体験・好きなものとの共通点を考えてみる
- 「驚き」なら新しさへの興味などの要素を考えてみる
- 面白さとは「共感」か「驚き」からくる。
「好き」を伝えるには?
- 相手との情報格差をうめる
- 相手との距離をつかむところから始まります。
- 知らない相手なら「あなたが興味ないことはわかっていますよ〜」というサインを最初にだすのをおすすめ
- 相手の興味のある枠があれば、それにあわせる
- 「読者」を決める
- 想定でOK。実際読むかは関係ない
- 「伝えたいポイント」を1点に決める
- 作者自身が伝わってほしいことを把握できずに書いた文章から、読者が勝手になにかを読み取ってくれるケースなぞほとんどない。
- 「工夫」しようとする志を持つ
- ただ感想を書くだけで作文にならない
- 調べたらわかることについても、長々と書かない。
- ありきたりも書かない。
- 書き出しを工夫する。
- 良かった要素(シーン)、書いてあることの予測、自分がたり、問いから始めるなど色々パターンがある
- 修正する
- 最後までラフに書いてみて後で修正するのが大事。
- 順番を買えたり、いらない文章をけずったり、みだしをつける。
おわりに
自分が感動した映画でも、評価が星2.5とかだと「あれ?」と自分の感情に疑いを持ったりすることが過去ままありましたが、自分が何故感動したか掘り下げる価値に気づかせてくれた本でした。「推しを語るスキル」はどの年代でも使える能力なので、少しでも磨いていきたいなっと。
リンク